「小論文には“型”があるんですか?」
「小論文には”型”があるんですか?」何度か塾の先生に尋ねた。小論文の評価はある程度の基準に従ってなされるのだから、“正解に近い型”のようなものがあってもおかしくないと思ったからだ。しかし先生は、「小論文の型みたいなものはない」と断言した。
でも、私は納得できなかった。
しかし、受験で求められる小論文には一定の型が必要だと感じていた。だから、先生が型を教えてくれないのなら、自分で型をつくるしかない、そう思った。
型のない世界に、自分なりのルールをつくる
私が大学編入試験を受けたのは45歳のとき。周囲の多くは現役大学生、あるいは20代の社会人。年齢の差を意識するよりも、自分の武器をどう磨くかに集中しようと思った。
小論文の学習に取り組むにあたり、私はふたつの方法を並行して進めた。
ひとつは、通信講座での学習。課題をメールで提出し、添削結果もメールで返ってくる形式だった。これは淡々と進められる反面、孤独感もあった。
もうひとつは、オンラインでの個別添削。こちらでは、すでに提出済みの課題を先生と一緒に見直し、ヒントをもらいながら修正していくプロセスがあった。やり取りの中で、なぜその表現では弱いのか、どうすれば主張がより明確になるのかを丁寧に学ぶことができた。
通信とオンライン、それぞれの長所を活かしながら、私は一つ一つの課題に向き合った。
書籍と講評の分析で見えてきた“自分なりの型”
「小論文の書き方」についての書籍は数多く出版されている。ネットでも無料で読める解説がたくさんある。それらを読み漁り、メモを取り、分析した。
それと同時に、塾の先生から返ってきた添削結果もすべて記録に残した。どこが良かったか、どこが弱いか、どんな表現が評価されたか。小さな違いの積み重ねを見逃さず、そこから傾向を探った。
そうしていくうちに、自分が“書きやすい”と思える構成や展開のパターンが少しずつ固まっていった。最初に問題提起をし、次に背景や原因を説明し、その上で自分の意見を述べ、具体例を交えて論証し、最後にまとめで締めくくる。
それが、私の“自分なりの小論文の型”になった。
過去問をひたすら解き、精度を高める
編入試験の時期が近づいてくると、私は全国の大学の過去問を集めはじめた。多くの大学がWeb上で過去問を公開している。なかには小論文の課題文や設問の詳細まで掲載されているものもあった。
それらを片っ端からダウンロードし、自分がつくった“型”にあてはめて、小論文を書いた。ひとつ書くごとに、第三者の目で読み直し、表現を整え、文字数を調整した。
求められる文字数が1000字なら、私は995〜1000字になるように仕上げた。過不足なく書き切る力は、小論文では重要だ。文字数制限は、内容を圧縮し、構成力を高める良い訓練になる。
結果がすぐに出るわけではない。でも確実に力になる
最初からうまく書けたわけではない。添削で返ってくる赤ペンの嵐に落ち込んだこともあった。でも、書いて、直して、また書いて……を繰り返すうちに、「文章のどこでつまずくか」「主張が伝わるか」を自分でも感じ取れるようになってきた。
書き終えた論文を読み返しながら、「ここは流れが弱いな」「この具体例は説得力がないな」と自分で修正案を考えられるようになった頃には、すでに“思考力”がついていた。
受験のための小論文学習だったけれど、その過程で得たのは、単なるスキルではなく「言葉を通して考え抜く力」だったように思う。
自分で考え、自分で型をつくるということ
結局のところ、小論文に“完璧な型”はないのだと思う。
けれど、自分に合った型、自分が納得して書ける形を見つけることは、すべての受験生にとって必要な作業だと思う。私は先生に答えを求めても得られなかったから、自分で探すしかなかった。でも、それがかえって良かったのかもしれない。
45歳で大学に編入するというチャレンジは、人生の中で大きな決断だった。そして、それを支えたのは、日々の小さな積み重ねだった。小論文の勉強も、同じだった。
どんなに遅く見えても、どんなに遠回りに見えても、 「自分で考え、自分で進む」ことに、無駄な時間などひとつもなかった。
あのとき作った自分なりの小論文の型は、今も文章を書く時だけでなく、人前での説明など、さまざまな場面で活きている。
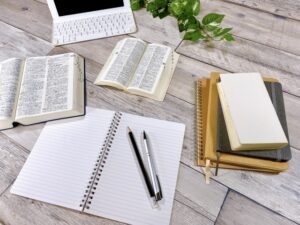


コメント